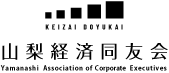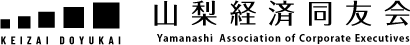経済人のコラム 時局寸評

この80年の山梨県

今年、私の勤務する日本銀行甲府支店は開業80周年を迎えます。
開業した日は7月23日と、終戦の約3週間前でした。
この時期に開業したのは、当時、政府関連機能を長野県の松代に移転することが計画されている中、東京日本橋にある日本銀行本店の松代への疎開をサポートする拠点として設けられたためです。
甲府支店は、現在の甲府商工会議所の地にあった山梨中央銀行相生町支店の店舗を譲り受けて、開業することになりましたが、ちょうど甲府大空襲があってから2~3週間後で、甲府市内は焼け野原となっていましたので、開業当初は大きな混乱があったようです。
その後、甲府支店は、山梨県の方々に支えられて、現在にいたるまで、業務を継続することができました。このことに思いを馳せると、山梨県の方々には感謝の気持ちでいっぱいになります。
同時に、この間、甲府支店がどのように山梨県を眺めてきたのかということも気になるところです。
そこで、開業してからの80年について、関係する資料や経済データに目を通してみたところ、いろいろと興味深いことが分かりました。
まず、人口ですけれども、
終戦後の1947年には80万人を超えていて、80万人を切ったと言われる現在とほぼ同じ人口規模でした。
その後の推移を5年刻みでみますと、1970年をボトムに約76万人まで減少します。
そこから反転して、ピークの2000年には89万人を超えることになります。
その後は、再び減少に転じて今にいたる訳ですが、この推移をみると、山梨県は一度人口減少を克服していることが分かります。
次に、農業の状況をみてみたいと思います。
山梨県は、フルーツ県としてのブランドを確立している訳ですが、これがいつからだったのかということを探ってみますと、
1955年時点では、県内の農業生産額に占めるフルーツのシェアは1割もありません。5割近くが米・麦等が占めていて、その次に、蚕繭(さんけん)、いわゆる「おかいこさま」が2割を占めています。
フルーツのシェアが初めて1位になるのは、5年刻みでみますと1970年のことで、シェアとしては3割弱です。
その後、フルーツはシェアを伸ばして1990年に初めて5割に達し、それから今に至るまで5割以上を維持しています。こうしてみますと、シェアという点からは、1990年にはフルーツ県としてのブランドを確立したと言えるかもしれません。
続いて、農業も含めた産業全体の状況をみてみますと、山梨県の経済構造が大きく転換したことが窺えます。
1955年における就業者の産業別の割合をみますと、農林水産業などの第1次産業が5割を超えています。
また、同年の県内総生産(県別GDP)の産業別の割合をみますと、第1次産業が25%を超えています(現在は1%台)。このように、1955年時点では、山梨県は経済的には農業県としての色彩が強かったようです。
その後、就業者および県内総生産でみて、徐々に製造業を含む第2次産業の割合を高めていくことになります。
1970年には、就業者の割合で第2次産業が第1次産業の割合を逆転します。
ちょうどこの頃、大型の工業団地である国母工業団地の供用が開始されます。この1970年は、先ほど述べたとおり人口減少が反転した年ですので、製造業の成長による県内の雇用吸収力の高まりが、その反転に寄与したことが推察されます。
1980年代に入ると、製造業大手の県内への本社移転や組織改編が相次ぎ、1985年には、県内総生産の45%を第2次産業が占めるようになります。その後も、今にいたるまでその割合は4割前後を維持しています。
この数字は、全国平均の約25%を大きく上回っていまして、山梨県は全国でも有数の工業県でもあります。
こうした経済構造の転換の背景の1つには、道路インフラの拡充がありました。特に、首都圏との地理的な近さを活かすうえで障害となっていた笹子峠の克服が、この間の山梨県の経済発展に大きな影響を与えたと考えられます。
まず、1958年に、国道20号に新笹子トンネルが開通します。
この開通までは、笹子峠を越える道が難所であったため、甲府-東京間のメインルートとして、御坂峠から富士吉田を経由する現在の国道137号が利用されていたようです。
このトンネルができたことで、甲府から東京までの道のりが、距離で30キロメートル、時間で1時間40分短縮され、これによって、甲府盆地で採取されたフルーツが、その日のうちに東京の市場に出荷することが可能になりました。
また、1982年には、中央道が、勝沼-甲府昭和間がつながることで全線開通し、このことが、先ほど述べた1980年代以降の製造業の隆盛に大きく寄与したものと思われます。
以上、極めて簡潔ではありますが、主に経済の側面から見たこの80年の山梨県を私なりに振り返ってみました。
今や、山梨県は、1人あたり県民所得で全国8位と全国有数の豊かな県になっています。
今後も、この山梨県が、蓄積された技術や優秀な人材、豊かな自然環境、首都圏に近接し、首都圏と北陸・東海地方の結節点になっている地理的な優位性といった長所を、予定されているリニア中央新幹線の開通や中部横断自動車道の延伸といった交通インフラの拡充によってさらに活かされることで、一段と発展していくことを祈願しています。